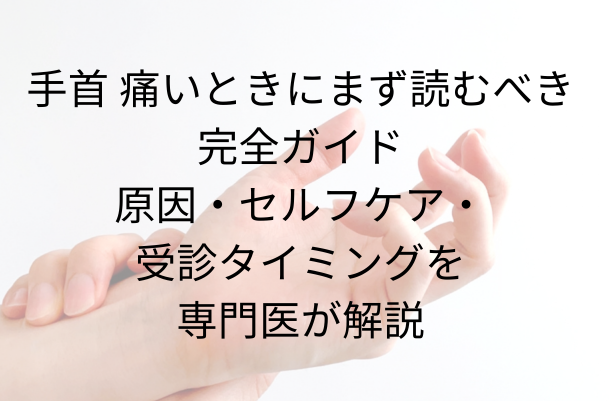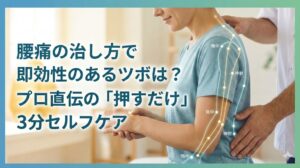手首 痛いと感じたあなたへ。原因の見分け方・即効のセルフケア・サポーターや治療法まで、専門医監修で分かりやすく解説します。症状別チェックリスト付きで、適切な対応のヒントが満載。
1.症状の種類と痛みの特徴で見分ける原因
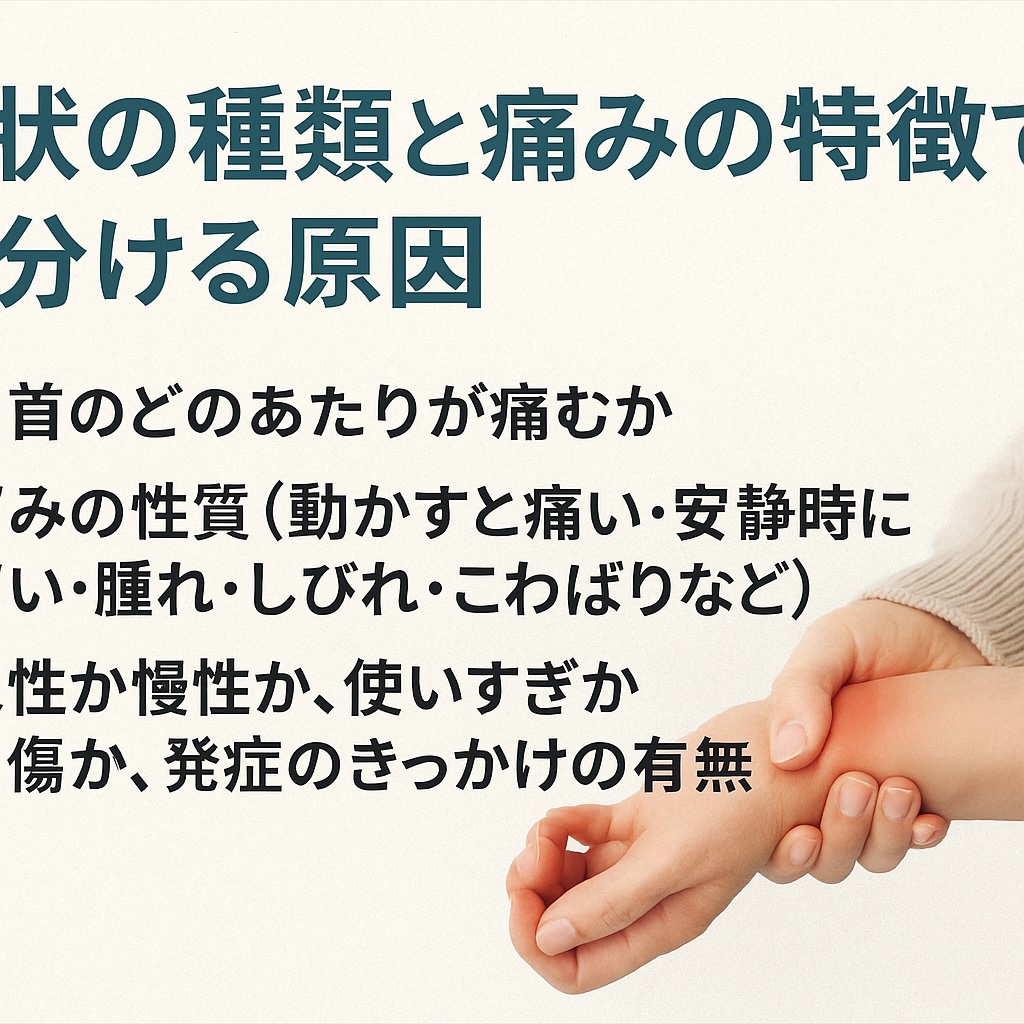
手首のどのあたりが痛むかを確認する
手首の痛みは、場所によって考えられる原因が異なると言われています。例えば親指側が痛む場合、ドケルバン病(腱鞘炎)や橈骨茎状突起炎など、使い過ぎによる腱や腱鞘への負担が関係していることがあります。一方、小指側に痛みがあるときは、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)や尺骨突き上げ症候群が疑われることがあるとされています。また、手首の中央や手のひら側がしびれるように痛む場合、手根管症候群など神経への圧迫が原因になることがあると言われています(引用元:湘南リウマチ膠原病内科、阿部整形外科クリニック、しんとう整形外科)。
痛みの性質を手がかりにする
手首を動かすと痛いのか、それとも安静にしていても痛むのかによっても判断の手がかりになるといわれています。動作時のみ痛い場合は、腱や靭帯への負担が考えられ、安静時にも痛む場合は炎症や神経圧迫が関係することがあるそうです。さらに、腫れ・熱感・赤みがあるときは炎症性の疾患(関節リウマチや痛風など)も疑われます。しびれやこわばりが朝方に強い場合もリウマチ性の関与が示唆されることがあるとされています(引用元:Ubie、湘南リウマチ膠原病内科、阿部整形外科クリニック)。
急性か慢性か・きっかけの有無を振り返る
痛みが突然強く出た場合は、転倒やスポーツによる捻挫・骨折といった外傷の可能性があります。一方、徐々に痛みが増してきた場合は、長時間のスマホ・パソコン操作や育児など、日常動作での使い過ぎが関係することが多いといわれています。特に繰り返しの負荷は腱や靭帯の微細な損傷を起こしやすいため、原因を思い返しておくことが大切とされています(引用元:阿部整形外科クリニック、リガクボディ、しんとう整形外科)。
#手首の痛み #腱鞘炎 #TFCC損傷 #手根管症候群 #手首の使い過ぎ
2.代表的な疾患・損傷とそのメカニズム

腱鞘炎(ドケルバン病など)
親指側の手首に痛みや腫れが出ることがあり、特に親指を動かすときに強く痛むのが特徴といわれています。腱が通る「腱鞘」と呼ばれるトンネル部分で炎症が起こり、動かすたびに摩擦が生じることで痛みが強まると考えられています。スマホ操作や育児で親指を酷使する人に多い傾向があるそうです(引用元:Ubie、しんとう整形外科・リウマチクリニック、阿部整形外科クリニック)。
手根管症候群
手のひら側の手首にある「手根管」というトンネルで、正中神経が圧迫されることで起こるとされています。指先のしびれや夜間の痛み、細かい動作がしづらいと感じることが多いと言われています。パソコン作業や更年期の女性に多い傾向があるとされ、手を振るとしびれが軽くなることもあります(引用元:パヤタイ病院、阿部整形外科クリニック)。
TFCC損傷(手首の小指側の軟部組織)
手首の小指側にある三角線維軟骨複合体(TFCC)が傷ついた状態を指します。手をついたりひねったあとに痛みが続いたり、小指側に荷重をかけると痛むことがあるといわれています。スポーツや転倒で生じやすく、関節の安定性が低下していると起こりやすいとされています(引用元:シンセルクリニック、阿部整形外科クリニック、しんとう整形外科・リウマチクリニック)。
骨折・捻挫・使い過ぎによる疲労性損傷
転倒や衝突での骨折や捻挫はもちろん、日常的な手の使いすぎによる疲労骨折も手首の痛みにつながることがあると言われています。疲労骨折は初期には軽い痛みだけのこともあり、気づかないまま悪化することもあるとされています(引用元:阿部整形外科クリニック、阿部整形外科クリニック、しんとう整形外科・リウマチクリニック)。
その他(関節リウマチ・痛風・関節炎などの炎症性疾患)
炎症性疾患でも手首の痛みが出ることがあるとされ、左右対称にこわばりが出たり、発熱や全身のだるさを伴う場合は関節リウマチなどが考えられるそうです。急に腫れて激しい痛みを感じるときは痛風の発作の可能性もあると言われています(引用元:湘南リウマチ膠原病内科、奥野祐次クリニック、しんとう整形外科・リウマチクリニック)。
#手首の痛み #腱鞘炎 #手根管症候群 #TFCC損傷 #関節リウマチ
3.セルフチェック方法と見分けるポイント

動作テストで手首の状態を確かめる
手首の痛みを確認するには、まず「どの動きで痛むか」を把握することが大切だと言われています。たとえば、手首を上下に曲げる・反らす・左右にひねるといった基本的な動きをゆっくり行い、どの方向で痛みが出るかを確認してみましょう。動かしているうちに引っかかる感じや、動かした直後にジーンとした痛みが残る場合は、腱や関節に負担がかかっている可能性があると考えられています(引用元:しんとう整形外科・リウマチクリニック、阿部整形外科クリニック)。
日常動作で痛みが出るシーンを把握する
普段の生活動作でも、どんなときに痛みが強まるのかを知ることで原因の手がかりになるとされています。スマホやパソコンを長時間使ったあとに痛む、重い荷物を持ったときにズキッとする、手をついたときにピリッとした痛みが走るなど、状況ごとに記録しておくとよいでしょう。繰り返しの負荷がかかっている場合、安静時には痛まないことも多いため、痛みが出るタイミングを把握することが役立つと言われています(引用元:しんとう整形外科・リウマチクリニック)。
腫れ・発熱・しびれなどの重症サインを見逃さない
もし手首が急に腫れて熱を持ち、触れるだけで強い痛みがある、または指先にしびれや感覚の鈍さが出ている場合は注意が必要とされています。これらは炎症や神経圧迫、感染などのサインのことがあるといわれており、早めに医療機関で相談することが推奨されています。無理に動かしたりマッサージをするのは避け、まずは安静を心がけると安心です(引用元:阿部整形外科クリニック)。
#手首の痛み #セルフチェック #動作テスト #手首の使いすぎ #重症サイン
4.応急対処法と日常でできるケア
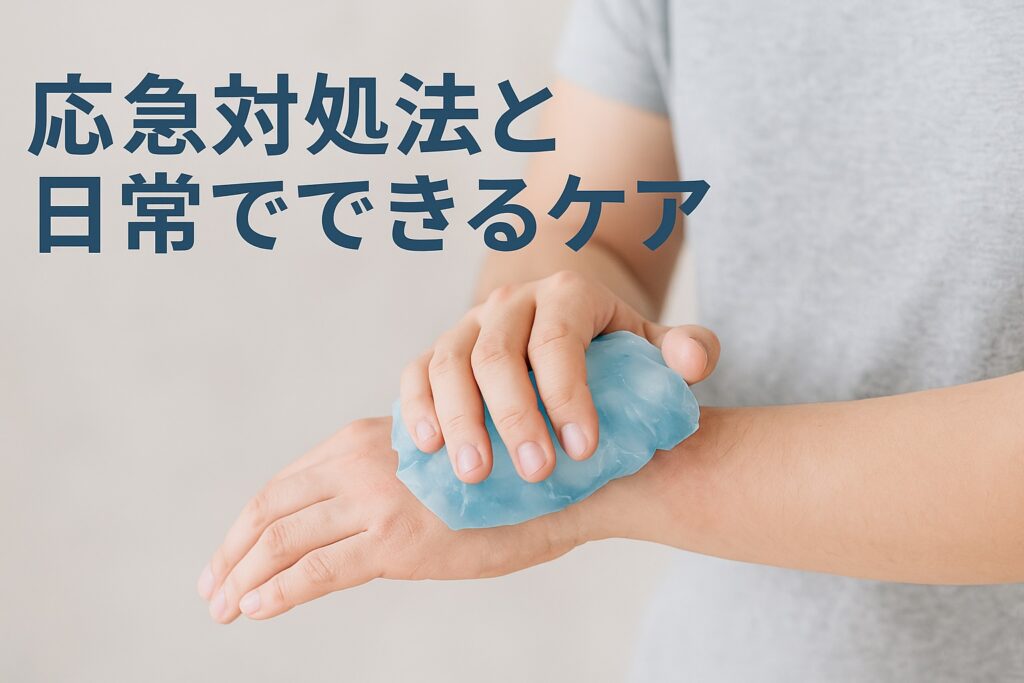
RICE法で炎症をやわらげる
手首に痛みが出た直後は、まず「RICE法」と呼ばれる基本的な応急ケアを試すことがすすめられています。RICEとは、安静(Rest)・冷却(Ice)・圧迫(Compression)・挙上(Elevation)の頭文字をとったものです。動かさずに休ませ、保冷剤などで軽く冷やし、軽く圧迫して腫れを防ぎ、心臓より高い位置に手を置いておくと炎症が落ち着きやすいと言われています(引用元:Ubie)。
サポーターやテーピングで負担を減らす
痛みがある間は、手首を安定させるためにサポーターやテーピングを使うのも有効とされています。手首の動きを制限しつつ支えることで、無意識に動かしてしまうのを防ぎ、回復しやすい環境を作るのに役立つそうです。装着はきつすぎず、血流を妨げないよう注意しながら、必要に応じて活用するとよいとされています(引用元:メディエイド)。
ストレッチやマッサージで血流を促す
炎症が落ち着いてきたら、前腕や手首周辺のストレッチや軽いマッサージで血行を促すことも大切といわれています。筋膜リリースのように優しくさすったり、手首をゆっくり回す動きを取り入れることで、こわばりが和らぐことがあるそうです。ただし痛みが強いときは無理に行わず、違和感がない範囲で行うのが安心です(引用元:理学ボディ)。
生活習慣を見直して再発を防ぐ
手首に負担をかけないよう、作業環境や使い方を見直すことも大切とされています。長時間同じ姿勢で作業するのを避け、休憩を挟む、スマホやパソコンは手首を反らさずに使うなど、日常のちょっとした工夫が再発予防につながると考えられています(引用元:阿部整形外科クリニック)。
#手首の痛み #RICE法 #サポーター活用 #手首ストレッチ #作業環境改善
5.受診するべきタイミングと治療の選択肢

どのような症状が出たら整形外科へ行くべきか
手首の痛みが長引いたり、日常生活に支障が出るほど強くなってきた場合は、整形外科で相談することがすすめられています。特に、手首が腫れて熱を持つ・指先にしびれや感覚の鈍さがある・夜間痛で眠れないといった症状があるときは、早めの来院が推奨されているそうです。痛みが一時的におさまっても再発を繰り返す場合も専門的な検査が役立つといわれています(引用元:阿部整形外科クリニック、奥野祐次クリニック)。
触診や画像検査で状態を確認する
整形外科ではまず触診で痛みの部位や動きの制限を確認し、その後必要に応じて画像検査を行うのが一般的とされています。骨や関節の変化を見るためにはX線(レントゲン)、靭帯や軟部組織の状態を詳しく知るにはMRI、炎症や血流を観察するには超音波検査が用いられることが多いといわれています(引用元:阿部整形外科クリニック、奥野祐次クリニック)。
保存療法と手術療法の選択肢
痛みが軽度であれば、安静・装具・消炎鎮痛薬・物理療法(温熱や電気刺激)といった保存療法が中心になることが多いとされています。一方、腱や靭帯が断裂している・神経の圧迫が強い・変形が進んでいるといった重度のケースでは、関節鏡を用いた損傷部位の縫合や固定などの手術療法が検討されることがあるとされています(引用元:札幌中央整形外科、阿部整形外科クリニック)。
リハビリと再発予防のポイント
症状が落ち着いてきたら、再発を防ぐためにリハビリを行うことが大切といわれています。可動域を取り戻すストレッチや筋力トレーニング、手首に負担をかけにくい動かし方の練習などが有効とされています。さらに、作業環境を見直し長時間同じ姿勢を避けることで、再び痛みが出るリスクを減らせると考えられています。
#手首の痛み #整形外科 #画像検査 #保存療法 #リハビリ