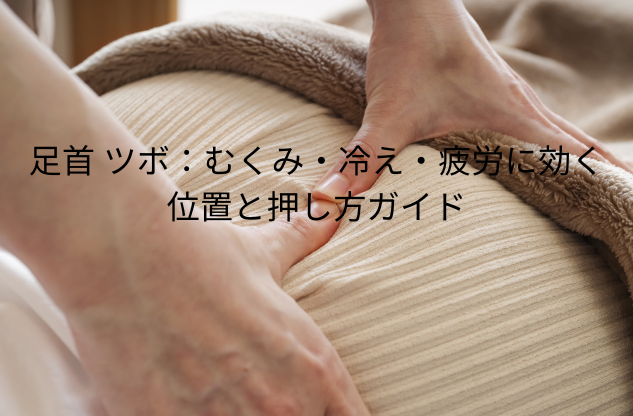足首 ツボの正しい位置と効果を徹底解説。むくみ・冷え・疲労などの症状別に、セルフケアでできる押し方や注意点も紹介します。
1.足首にある代表的なツボとその位置
「足首って、思ったよりツボが多いんだね」と感じたことはありませんか?
実は、足首のまわりには血流や自律神経、冷え対策に関係すると言われているツボがいくつかあります。まずは場所を知ることから始めましょう。

崑崙(こんろん):外くるぶしとアキレス腱の間にあるツボ
外くるぶしのすぐ後ろ、アキレス腱との間にあるくぼみが「崑崙(こんろん)」です。
ここは、足の疲れやむくみのケアに使われることが多く、血流を整える働きがあると言われています。指で軽く押すと心地よい痛みを感じる位置が目印です。
丘墟(きゅうきょ):外くるぶしの下前方にあるツボ
外くるぶしの少し下、甲側に向かって指を滑らせたあたりのくぼみにあるのが「丘墟」です。
長時間立ち仕事や歩行で重だるく感じるとき、この部分を軽く刺激すると楽になる場合があるそうです。
申脈(しんみゃく):外くるぶしの真下のくぼみ
外くるぶしの真下にある小さなくぼみが「申脈」と呼ばれています。
このツボは、自律神経を整えるサポートに使われると言われており、疲れが抜けづらいときや寝つきが悪いときに押す人もいるそうです。
太谿(たいけい):内くるぶしとアキレス腱の間
内くるぶしのすぐ後ろ、アキレス腱の内側のくぼみが「太谿(たいけい)」です。
冷え性や足のこわばりが気になる方にすすめられることが多く、足首を温めながら軽く押すとより効果的だと言われています。
お風呂上がりに深呼吸をしながら押すと、体全体がじんわり温まる感覚を覚える方もいるようです。
足首のツボはどれも「くぼみ」が目印。まずは鏡を見ながら位置を確認してみましょう。慣れてくると、左右の違いや筋肉の張り具合も自然とわかるようになります。
#足首ツボ #崑崙 #丘墟 #申脈 #太谿
2.ツボごとの期待効果と適応症状
足首のまわりには、「むくみ」「冷え」「だるさ」「関節の痛み」など、日常で感じやすい不調と関係しているツボが多いと言われています。ここでは、前章で紹介した4つの代表的なツボを中心に、それぞれの特徴と期待される効果を見ていきましょう。
「押すだけで少し楽になる気がする」と感じるのは、筋肉や血流、自律神経に穏やかに作用しているからかもしれません。

崑崙(こんろん):足のむくみ・疲労にアプローチ
「立ち仕事のあと、足首がパンパンに…」というときに使われることが多いのが崑崙です。外くるぶしとアキレス腱の間にあるこのツボは、血行を促す働きがあると言われています。
ふくらはぎや足の甲まで重だるいときに、軽く押してあげるとスッと楽になるという声もあります。押すときは、指先で円を描くようにゆっくり刺激するのがポイントです。
丘墟(きゅうきょ):冷えや足首のこわばり対策に
外くるぶしの下前方にある丘墟は、足首の柔軟性や冷え対策に関係しているとされるツボです。長時間座りっぱなしや、冷房で足元が冷えるときに押すと、血流が整いやすいと言われています。
「冷えが取れる感じがする」と話す人もいますが、強く押しすぎず、心地よい程度の力で数秒キープするのがコツです。お風呂上がりなど、体が温まったタイミングで行うとより実感しやすいでしょう。
申脈(しんみゃく):自律神経の乱れを整えるサポート
外くるぶしの真下にある申脈は、自律神経のバランスを整えるサポートに使われることがあるツボです。ストレスや不眠、全身のだるさを感じるときに押すと、心身が落ち着く感覚を覚える人もいるそうです。
ただし、体調が悪いときや発熱時などは避けたほうがよいとされています。刺激は「気持ちいい」と感じる程度にとどめ、深呼吸をしながら行うとよりリラックスしやすいです。
太谿(たいけい):冷え性や関節の痛みに使われるツボ
内くるぶしの後ろにある太谿は、冷え性や関節の違和感に使われるツボとして知られています。腎経(じんけい)という経絡の流れに位置しており、体の内側から温めるサポートをするとも言われています。
冬場や冷えやすい女性に人気があり、足湯や温タオルと組み合わせるとより心地よいケアになります。軽く押しながら深呼吸をすると、体全体がほぐれていくような感覚を得られる人も多いようです。
足首のツボは、どれも強く押しすぎないことが大切です。ツボ刺激は「体の声を聞く時間」と考えて、1〜2分ほどゆっくり向き合ってみましょう。
#足首ツボ #崑崙 #丘墟 #申脈 #太谿
3.セルフケアでできる押し方・刺激方法
ツボ押しは、特別な道具がなくても日常の中で取り入れやすいセルフケアの一つだと言われています。足首のツボを押すときは、ただ「痛気持ちいい」だけで終わらせず、呼吸やタイミングを意識するとより効果的です。ここでは、指圧・ツボ押し棒・ローラーなどを使った実践的な方法を紹介します。

基本の指圧法:親指でゆっくり5秒キープ
最もシンプルなのは、親指を使って軽く押す方法です。
足首のツボに指を当て、5秒ほどゆっくり押してから離す──これを3〜5回繰り返すだけでOKです。力を入れすぎると筋肉を傷める可能性があるため、「少し痛いけど気持ちいい」と感じる程度がちょうど良いと言われています。
お風呂上がりや寝る前など、体が温まっているタイミングに行うと血流が促されやすいそうです。
ツボ押し棒・ローラーの活用法
指で押しにくい人は、ツボ押し棒やローラーを使うのもおすすめです。
特に「丘墟」や「崑崙」のように足の外側にあるツボは、指だと角度が難しいこともあります。棒を使うと圧が均一になりやすく、短時間でピンポイントに刺激を与えられると言われています。
ただし、金属製など硬すぎるものは避け、木製や樹脂製のやわらかい素材を選ぶのが安心です。
押すタイミングと呼吸の合わせ方
「いつ押せばいい?」とよく聞かれますが、おすすめは入浴後と寝る前です。血行が良くなっているときに行うと、筋肉がリラックスして刺激が伝わりやすいと言われています。
押すときは呼吸を止めず、息を吐きながら押し、吸いながらゆるめるのがコツです。これにより自律神経のバランスが整いやすく、リラックス効果が高まると考えられています。
注意点とセルフチェック
ツボ押し中に「ズキッ」と鋭い痛みを感じたり、押した後に腫れや赤みが出た場合は中止しましょう。体が冷えているときや疲労が強いときも無理は禁物です。
また、「昨日より押すと痛い」「左右で感じ方が違う」などの変化をメモしておくと、自分の体調の目安になります。継続して行うことで、少しずつ自分の体との付き合い方がわかるようになると言われています。
続けるコツ:ながら習慣にする
「テレビを見ながら」「ドライヤーをかけながら」など、**“ながらツボ押し”**を取り入れると続けやすいです。1回5分以内でも十分。毎日のちょっとした習慣が、足首まわりの軽さや温かさにつながると感じる人も多いそうです。
#足首ツボ #セルフケア #ツボ押し #リラックス #血行促進
4.足首ツボと併用したケア方法
ツボ押しを単独で行うよりも、「ストレッチ」や「温め」などのケアを組み合わせることで、より心地よい変化を感じやすいと言われています。特に足首まわりは血流が滞りやすく、日常生活で疲れがたまりやすい部分です。ここでは、ツボ刺激と相性の良いケアを5つ紹介します。すべて自宅でできる簡単な方法なので、無理のない範囲で試してみましょう。

① 足首ストレッチで可動域を広げる
ツボを押す前後に軽くストレッチを入れると、筋肉がゆるみ刺激が伝わりやすくなると言われています。
やり方は簡単で、座ったまま片足を前に伸ばし、足首をゆっくり回すだけ。時計回りに5回、反対回りに5回が目安です。動かすときは息を止めず、呼吸を続けながら行いましょう。「動かしながら押す」よりも、「ほぐしてから押す」方が安全です。
② 足浴で温めながらツボを刺激
お湯を張った洗面器に足首まで浸け、10分ほど温めます。温度は38〜40℃程度のぬるま湯が目安です。
血行が良くなることでツボ周辺の筋肉がやわらかくなり、指圧の刺激が伝わりやすくなると言われています。
ラベンダーやユズのアロマオイルを数滴加えると、香りのリラックス効果もプラス。足浴後は水分補給を忘れずに。
③ 軽いマッサージで流れを整える
ツボ押しと並行して、ふくらはぎから足首にかけてやさしくさすり上げると、リンパや血液の流れがスムーズになると考えられています。
ポイントは「強く揉まないこと」。クリームやオイルを使って、肌への摩擦を減らしながら行うと快適です。むくみを感じやすい方は、朝より夜に行う方がリラックス効果を得やすいようです。
④ 温めケアで冷え対策をプラス
ツボ押しの前にホットタオルを足首に巻くのも効果的だと言われています。温めることで血管が広がり、押したときの刺激がやわらかく伝わります。
冷え性の方は、夜寝る前に湯たんぽを足元に置いたり、靴下を重ね履きするなどの工夫も◎。
特に「太谿(たいけい)」の周辺を温めると、全身がポカポカしてくる感覚を覚える人も多いようです。
⑤ 軽い運動でツボの効果をサポート
ツボ押しを習慣にするだけでなく、歩く・足首を動かすこと自体も大切です。
散歩やヨガ、軽いストレッチなど、足首を自然に動かす運動を取り入れることで、ツボ刺激の相乗効果が期待できると言われています。
特に朝の軽いウォーキングは、全身の血流が整いやすく、一日を軽やかに過ごせるきっかけになります。
「押して」「温めて」「動かす」——この3つの流れを意識すると、足首ツボのケアはより効果的になります。毎日の生活の中で、気持ちいいと思えるリズムを見つけていくのが続けるコツです。
#足首ツボ #ストレッチ #足浴 #温めケア #マッサージ
5.押す際の注意点・やってはいけないケース
ツボ押しは手軽にできるセルフケアとして人気ですが、間違った方法やタイミングで行うと、体に負担をかけてしまうことがあると言われています。
「ちょっと強く押した方が効きそう」と感じる方もいますが、刺激が強すぎると逆効果になることも。ここでは、安全にツボ押しを続けるための注意点を紹介します。

強すぎる刺激はNG
「痛い方が効く」と思って、力を入れすぎていませんか?
ツボは神経や血管が集まるデリケートな部分です。強い刺激を与えると、筋肉の防御反応で逆に硬くなったり、内出血を起こす可能性があると言われています。
目安は「心地よい痛みを感じる程度」。押した後に赤く腫れたり、ズキズキするようならやりすぎのサインです。
炎症やケガがある時は避ける
捻挫や筋肉痛、すり傷など炎症を起こしている部位にツボ押しを行うのは避けましょう。
炎症部分を押すと痛みが強まり、回復が遅れることがあると言われています。
もし足首の腫れや熱感がある場合は、まずは安静・冷却を優先し、ツボ押しは炎症が落ち着いてから行うのがおすすめです。
妊娠中・生理中の刺激は慎重に
妊娠中や生理中の女性は、体がデリケートな状態にあります。
特に足首のツボの中には、子宮や骨盤の血流に関係すると言われるポイントもあるため、過度な刺激は避けた方がよいとされています。
「押していいか迷うとき」は、専門家(鍼灸師や整体師)に相談するのが安心です。
体調が悪いときや発熱時は控える
風邪や発熱など、体が弱っているときにツボ押しをすると、疲労感が増すことがあるそうです。
これは、ツボ押しによって一時的に血流や代謝が変化し、体に負担がかかるためだと考えられています。
体調が整ってから再開する方が、ツボ刺激の心地よさを感じやすいでしょう。
来院を検討すべきケース
ツボ押しをしても「痛みが続く」「腫れが引かない」「しびれがある」場合は、整形外科や整骨院などで専門的な確認を受けることがすすめられています。
ツボの問題ではなく、関節や神経のトラブルが関係していることもあるためです。
早めの来院で、必要な検査や施術を受けられると安心です。
無理に押さない、痛みを我慢しない、体調に合わせる──この3つを意識するだけでも、安全で効果的なセルフケアにつながると言われています。ツボ押しは「気持ちいい」と感じる範囲で続けていくのが理想です。
#足首ツボ #ツボ押し注意点 #セルフケア安全 #押しすぎ注意 #来院目安