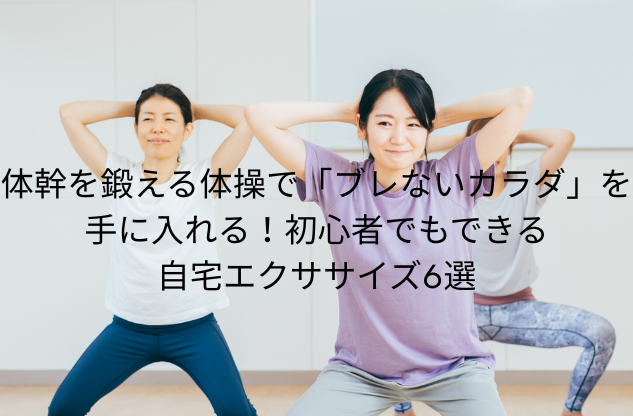体幹を鍛える体操を始めてみたいあなたへ。姿勢改善・腰痛予防・運動パフォーマンス向上に効く自宅でできる6つの簡単エクササイズを、初心者向けに分かりやすくご紹介します。
1.体幹って何?まずは「鍛える目的」とメリットを知ろう

体幹の定義と、意外と知られていない役割
体幹という言葉はよく聞きますが、「どの部分を指すのか?」と改めて考えると少し曖昧に感じる方も多いようです。体幹とは、一般的に“頭・腕・脚を除いた胴体部分の筋肉”をまとめた呼び方と言われています。とくに、腹部・背中・骨盤周りの筋肉が中心で、姿勢を支えたり、動作の土台になる働きがあると説明されています。
私たちがまっすぐ立ったり、歩いたり、物を持ち上げたりできるのは、体幹が働いて体のブレを抑えてくれるためとされています。「筋トレをしていないのに、妙に疲れやすい」「姿勢が崩れやすい」という人は、体幹の筋肉が弱まっている可能性があるとも言われています。
体幹を鍛える目的は“体を整える土台づくり”
体幹を鍛える目的として多く挙げられるのが、“姿勢の安定”です。デスクワークやスマホ使用時間が長い現代では、気づかないうちに背中が丸くなったり、反り腰になったりしやすいと言われています。体幹の筋肉が働きやすくなると、自然と姿勢が整いやすくなり、体の負担が軽くなる傾向にあるようです。
また、日常生活の動作がスムーズになることもよく語られています。例えば、階段の上り下りや長時間の歩行、買い物中の荷物の持ち運びなど、体の中心が安定することで動作全体が楽になると感じる人もいるようです。「体幹を鍛える体操」というキーワードが注目されるのも、こうした日常の快適さにつながりやすいと考えられているためと言われています。
体幹トレーニングによって期待されているメリット
体幹を鍛えることによって期待されている主なメリットとしては、以下のような点があります。
- 姿勢が整いやすくなると言われている
- 腰や肩周りの負担が軽減しやすいとされている
- スポーツや運動のパフォーマンス向上につながるとされている
- 呼吸がしやすくなるケースもあると言われている
もちろん、これらは個人差があるため必ずしも誰にでも当てはまるわけではありませんが、「全身の安定性を高める」という体幹の性質を考えると、こうした効果が得られやすいと考えられているようです。
体幹は“鍛えるほど日常の質が上がりやすい部分”とも言われており、軽めの体操から始めても取り入れやすいのが魅力です。まずは無理なくできる範囲で、体幹に意識を向けてみるのも良いきっかけになるかもしれません。
#体幹とは
#体幹を鍛える目的
#体幹のメリット
#姿勢改善のポイント
#体幹エクササイズ準備OK**
2.まずチェック! 自分の体幹力を知るセルフチェック方法
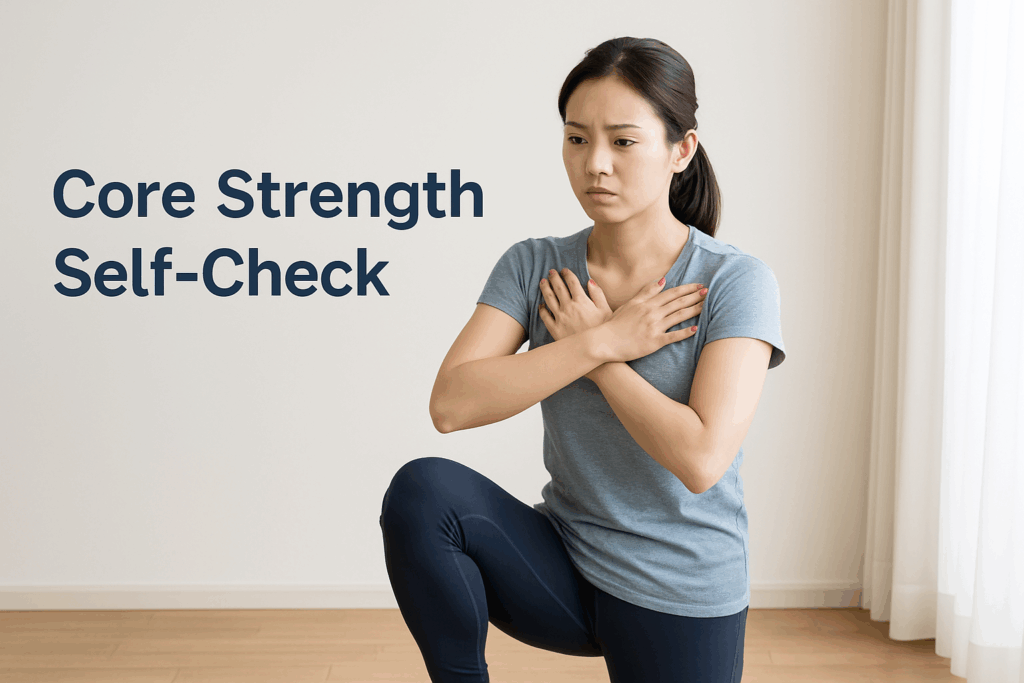
最初に確認しておきたい「体幹が働いているかどうか」の目安
体幹を鍛える体操を始める前に、「そもそも自分の体幹はどれくらい働いているのか?」を知っておくと役に立つと言われています。実際、体幹が弱まりやすい生活習慣は多いと言われており、長時間のデスクワークやスマホ姿勢が続くほど、お腹や背中の筋肉が使われづらくなる傾向があるとされています。
こうした背景から、体幹が安定しているかどうかを簡単にチェックする方法が注目されているようです。「特別な道具がないとできない?」と聞かれることもありますが、家で試せるものが多く、数分あれば確認できると言われています。
片脚立ちチェックでわかる安定性の目安
まず試してほしいのが、片脚立ちのチェックです。やり方はシンプルで、腕を組んで片脚を軽く上げ、20〜30秒ほどキープを目安にします。ここでグラつきが大きかったり、途中で姿勢が崩れやすい場合は、体幹の筋肉がスムーズに働きにくい状態かもしれないと言われています。
「片脚立ちは得意なんだけど?」と感じた人でも、目を閉じると一気にバランスが取りにくくなるケースもあります。これは視覚に頼らず体幹の働きを確かめる方法としてよく紹介されているものの一つです。
プランク姿勢でチェックする“体のブレ”
もう一つの定番が、プランク姿勢のセルフチェックです。肘とつま先で体を支える形ですが、そのまま30秒保つだけでも体幹がどれくらい安定しているか目安にしやすいと言われています。もし腰が反りやすかったり、お腹の力が抜けてしまう場合は、胴体の筋バランスが整いにくい状態かもしれないと考えられています。
一方で、「きついのは良いサイン?」という質問をもらうことがありますが、体幹は“痛みが出るほど力む必要はない”とも言われています。無理のない範囲で確かめてみるのが安心です。
日常動作の中でも気づけるチェックポイント
セルフチェックは運動の場面だけでなく、日常動作でも可能です。たとえば、
- 長時間座っていると姿勢が保ちづらい
- 歩いていると肩が左右に揺れやすい
- 片手で荷物を持つと腰が引っ張られる感じがする
こうしたサインがある場合、体幹が安定しづらいと言われることがあります。体幹を鍛える体操を始める前の“現状把握”として、普段のくせをチェックしておくのも役立つと言われています。
#体幹セルフチェック
#片脚立ちの目安
#プランクで確認
#日常動作と体幹
#体幹を鍛える体操準備
3.自宅でできる「体幹を鍛える体操」6選(初心者〜中級者向け)
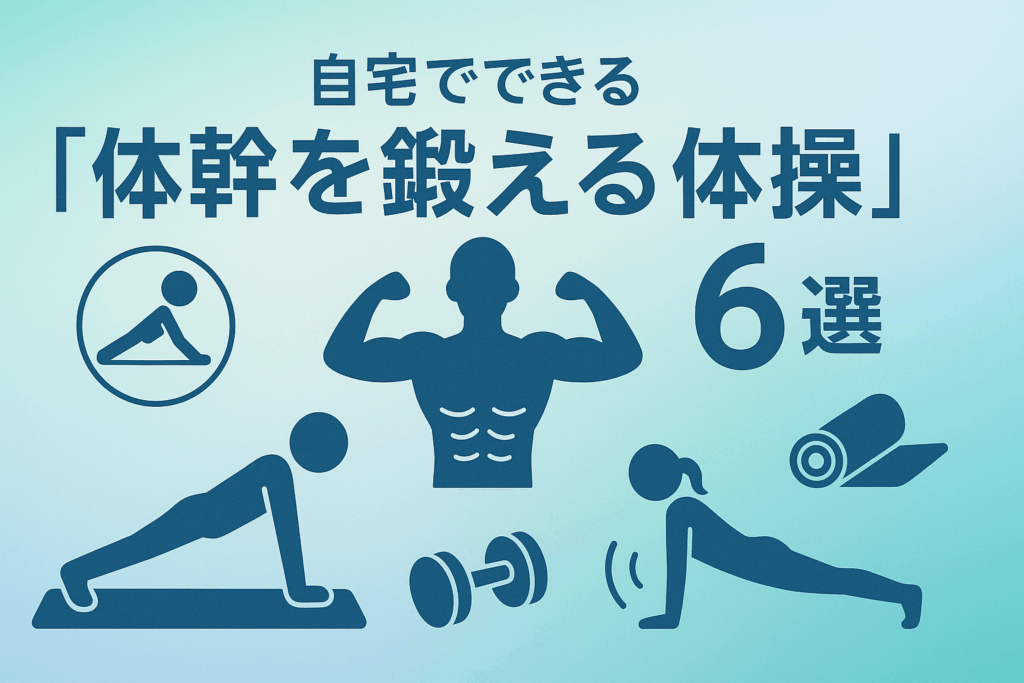
①ドローイン(呼吸を使った基礎エクササイズ)
まず紹介されることが多いのが、呼吸を利用したドローインです。やり方は、お腹に軽く手を添えて、息を吐きながらゆっくり凹ませるだけと言われています。呼吸と連動して体幹が働きやすくなるため、初心者でも取り入れやすいと紹介されています。
「お腹をへこませる感覚が分かりづらい…」という声もありますが、最初は数秒からでも問題ないと言われています。
②基本のプランク(静止姿勢で体幹を意識)
プランクは体幹を鍛える体操として有名で、肘とつま先で体を支えてキープします。背中が丸まりやすかったり、腰が反りやすい場合は負担がかかるため、無理せず姿勢を確認しながら行うのがおすすめと言われています。
「30秒でも結構きつい…」という人も多いですが、少しずつ慣れることで体幹が働きやすくなると考えられています。
③サイドプランク(左右差の確認にも)
横向きになり、片肘で体を支えるサイドプランクも取り入れやすい体操です。左右どちらが安定しづらいか確認でき、骨盤の位置も分かりやすいと言われています。腰が落ちやすい場合は、膝をついた形で軽く行う方法も紹介されています。
④バックエクステンション(背面の体幹を意識)
うつ伏せで上半身を軽く持ち上げる動きで、背中から腰付近にかけての筋肉を使いやすい体操です。「反りすぎると負担が出やすい」とも言われているため、痛みがある日は避けたほうが安心です。
背面の体幹は意識しづらい部分ですが、日常の姿勢にもつながりやすいと考えられています。
⑤レッグレイズ(下腹部を優しく刺激)
仰向けで両脚を上げ下げするレッグレイズは、反動を使わず丁寧に行うことがポイントとされています。腰が浮きやすい人は、片脚ずつの動きから始めても負担を抑えやすいと言われています。
「下腹がプルプルする感じがする」と話す方もいますが、その揺れは体幹が踏ん張っているサインとして紹介されることがあります。
⑥イスを使った簡単エクササイズ(在宅ワーク中にも)
イスに浅く座り、背筋を軽く伸ばしたまま片脚を少し上げる動きも、体幹を鍛える体操として紹介されることがあります。負荷は軽めですが、姿勢キープの練習にもなると言われています。
「運動の時間が作りづらい」という方でも、休憩ついでに取り入れやすいのが魅力です。
#体幹を鍛える体操
#自宅エクササイズ
#体幹初心者向け
#プランクのポイント
#ドローインで基礎作り
4.注意したいポイント・やってはいけないこと
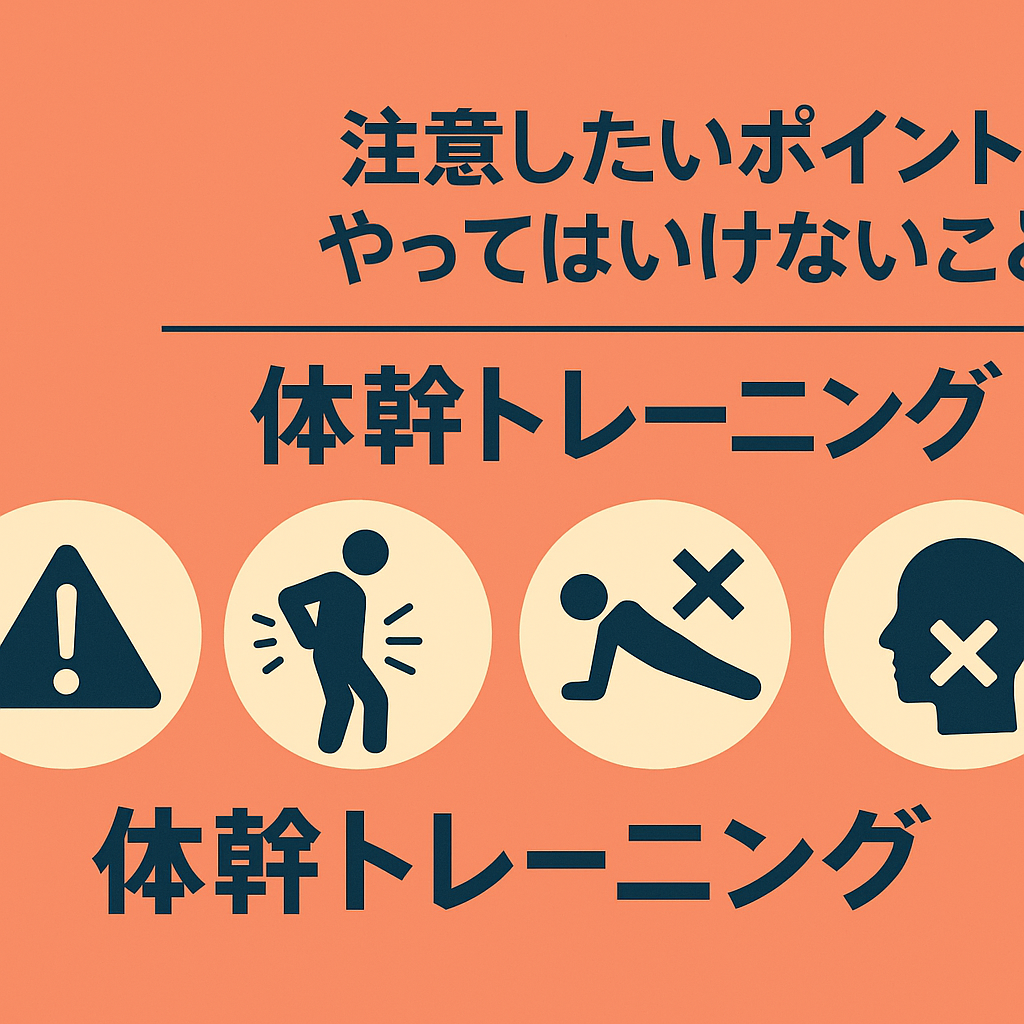
無理なフォームで続けると負担になりやすいと言われています
体幹を鍛える体操は自宅でも取り入れやすい反面、フォームが崩れやすいとも言われています。たとえば、プランクでは腰が反りやすく、サイドプランクでは骨盤が落ちやすいと紹介されることがあります。見た目では気づきにくいのですが、腰や首に力が入りやすくなるため、「ちょっと違和感があるな…」と思った時点で一度動きを見直すほうが安心だとされています。
勢いをつけすぎる動きはケガにつながりやすいと言われています
レッグレイズやバックエクステンションなど、脚や背中を動かす体操は反動を使いやすいと言われています。勢いで持ち上げてしまうと、本来意識したい体幹の筋肉が使われづらくなるため、動作はゆっくり行うほうが良いと紹介されることがあります。
「速くやったほうが効きそう?」と聞かれることもありますが、体幹では“スピードより丁寧さ”が大切だとされています。
痛みがある日は無理をしないほうが良いとされています
「ちょっと張るくらいなら大丈夫?」と思いがちですが、痛みがある時に体幹トレーニングを続けると負担が増えやすいと言われています。とくに腰まわりの違和感は、フォームの乱れや過度な緊張が原因のこともあるため、休息したり別の軽い体操に切り替えるほうが安心だとされています。
また、強い痛みやしびれが続く場合は、専門家に相談する例も多いと紹介されています。
呼吸を止めたままだと効果が出にくいとも言われています
ドローインやプランクのような静止系の体操は、つい呼吸を止めやすいとされています。呼吸が浅くなると、お腹や背中に力が入りにくくなるため、「苦しくなってきたかも」と感じたら、一度深呼吸を挟むだけでも体幹が働きやすいと言われています。
#体幹トレーニングの注意点
#フォームの見直し
#反動を使わない動き
#痛い日は無理しない
#呼吸と体幹エクササイズ
5.継続&効果を出すための“コツ”と次のステップ
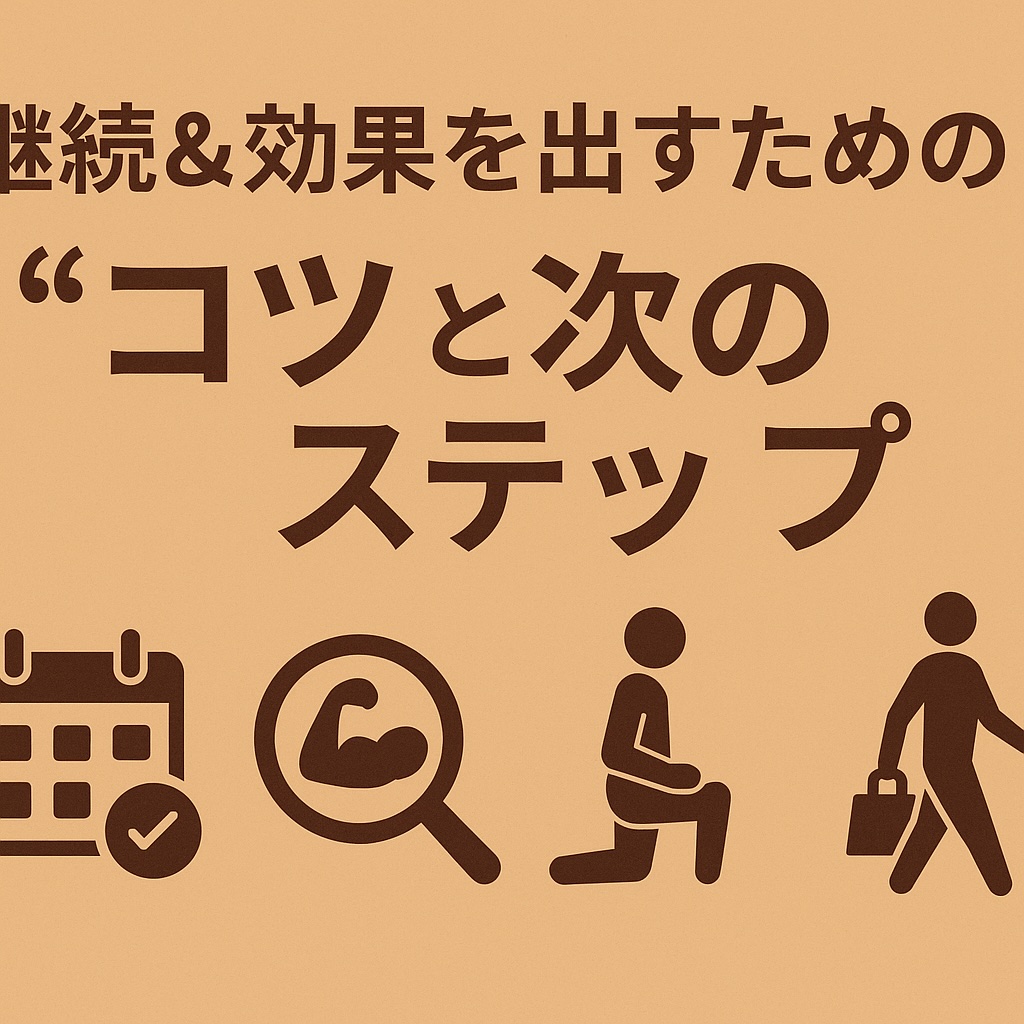
続けられる人が意識している「小さな習慣化」のコツ
体幹を鍛える体操は、1回の負荷より“続けること”が大事だと言われています。よく聞くのが「毎日30分はきついけれど、3分なら続けられる」という声です。まずは短時間でも、決まったタイミングで取り組むだけで習慣化しやすくなると言われています。
たとえば、「朝のコーヒーの前にプランク30秒」「寝る前にドローインを3〜5回」のように、日常の動作にセットする方法は続けやすく、多くの人が実践していると紹介されています。
効果を感じやすくする“フォーム確認”という次のステップ
慣れてくると、つい動作が雑になりやすいと言われています。そこで、週に1〜2回は「鏡を見ながらフォームを確認する」「スマホで横からの姿勢を撮ってみる」といったチェック方法を取り入れる人も多いとされています。
体幹トレーニングの効果はフォームの質に左右されやすいと紹介されることがあり、動作の丁寧さが体幹の働きやすさにつながると言われています。
負荷を上げるより“バリエーションを広げる”のが安全と言われています
「プランクに慣れてきたら時間を伸ばしたほうがいい?」という質問を受けることがありますが、時間を長くするよりも、横向きのサイドプランクや片脚プランクなど、別のバリエーションに切り替えるほうが体の負担が少なく、体幹全体を使いやすいと言われています。
時間だけを増やすと、腰や肩の負荷が増えやすいという意見もあるため、ステップアップは“種類を変える”ほうが安全なケースもあると紹介されています。
日常動作とつなげると体幹が意識しやすいと言われています
さらに次のステップとして、日常生活に「体幹を意識する場面」を増やす方法もあります。
・買い物中に荷物を左右バランスよく持つ
・長時間座る時はお腹を軽く引き込む
・歩く時に姿勢を整える
こうした小さな意識は体幹トレーニングと相性が良いと言われており、日常のクセ改善にもつながりやすいとされています。
#体幹トレーニング継続のコツ
#小さな習慣化
#フォーム確認の重要性
#バリエーションでステップアップ
#日常に活かす体幹意識