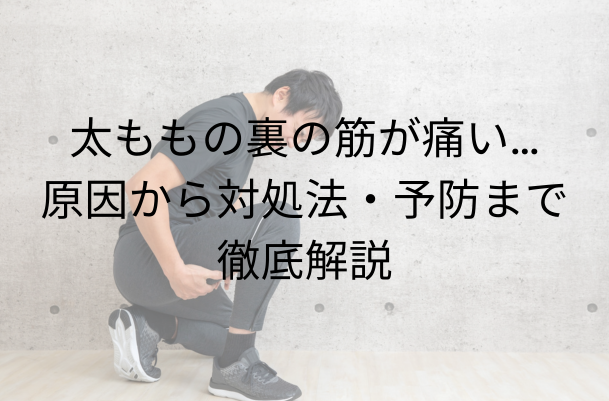太ももの裏の筋が痛いと感じたとき、放っておくと悪化することも。筋肉・神経・腱の観点から原因を整理し、今すぐできるセルフケアや受診目安、予防ポイントまでを分かりやすく解説します。
1.痛みを感じる「部位・症状」の整理

太ももの裏(お尻寄り〜膝近く)それぞれの痛みの特徴
太ももの裏の筋が痛いとき、その位置によって原因が少し異なると言われています。お尻に近い部分が痛む場合は「ハムストリングスの付着部炎」や「坐骨神経の圧迫」が関係していることが多いとされます。一方で、太ももの中央あたりの痛みは、筋肉の張りや軽い肉離れの初期段階が影響するケースが見られます。膝の近くで痛みを感じる場合には、膝裏の筋膜や腱の緊張が強くなっていることが考えられるそうです。
「同じ太ももの裏」でも、どの位置が痛いかを意識すると原因の目安が見えやすくなると言われています。
(引用元:リハサク https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/、にっこり鍼灸整骨院https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6042.html、メディカルID https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/)
「筋が痛い」と感じるときによくある違和感(ズキズキ/突っ張る/ピリッと)
太ももの裏が「ズキズキする」「突っ張る」「ピリッと電気が走るように痛い」といった感覚を持つ人も多いです。ズキズキした痛みは筋線維の微細な損傷による炎症反応が関係している場合があり、突っ張るような違和感は筋肉の過緊張や柔軟性の低下が影響していることがあります。ピリッとした痛みは、坐骨神経が刺激を受けている可能性もあるとされています。こうした“痛みの質”を把握しておくことで、原因の絞り込みにつながることが多いと言われています。
セルフチェック:いつ・どんな動作で痛むかを分類
次のような場面で痛みが出るかを整理すると、自分の体の状態がわかりやすくなります。
- 朝起きた直後に痛む → 寝ている間の姿勢や筋のこわばりが影響していることがある
- 長時間座ったあとに立ち上がると痛む → 坐骨神経への圧迫や骨盤周囲の筋緊張が関係するケースがある
- 階段の上り下りや歩行で痛む → ハムストリングスの疲労・硬直、または軽い肉離れの可能性も
- スポーツ中(ダッシュ・ジャンプ)で痛む → 筋肉の伸びすぎ・収縮バランスの乱れによる損傷リスク
このように「どんな動作で痛むか」を記録しておくと、改善の方向性を立てやすいとされています。無理をせず、痛みが強い場合は専門機関への相談を検討すると安心です。
(引用元:足裏屋クリニック https://ashiuraya.com/information/太ももの裏の筋が痛い|原因を探ってセルフケア/)
#太ももの裏の痛み
#ハムストリングス
#坐骨神経痛
#セルフチェック
#筋肉の張り
2.考えられる主な原因3つ

筋肉・腱・付着部の損傷(例:ハムストリングスの肉離れ・付着部炎)
太ももの裏の筋が痛いとき、最も多い原因の一つが「ハムストリングス(大腿二頭筋・半膜様筋・半腱様筋)」の損傷と言われています。特に運動中の急なダッシュやストレッチ動作で無理な伸び方をしたときに、“ピキッ”とした痛みが走ることがあります。軽度の場合は筋線維の一部に微細な損傷が起き、中程度になると腱や筋膜まで炎症が広がることもあるそうです。また、お尻に近い付着部(坐骨結節)で炎症が起こる「ハムストリングス付着部炎」もよく知られています。この場合、座っているときに痛みが強くなる傾向があると言われています。早めに冷却や安静を取り入れ、必要に応じて専門家の検査を受けることがすすめられています。
(引用元:リハサク https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/、にっこり鍼灸整骨院https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6042.html、メディカルID https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/)
神経が関係する痛み(例:坐骨神経痛・梨状筋症候群)
太ももの裏が「ピリッ」「ビリビリ」とするような痛みの場合、神経が関係していることがあるとされています。代表的なのが「坐骨神経痛」で、腰からお尻、太ももの裏を通る坐骨神経が圧迫または炎症を起こすことで症状が出ることがあります。長時間の座位や、腰を反らす動作で悪化するケースもあるようです。また、「梨状筋症候群」と呼ばれる状態では、お尻の奥にある梨状筋が硬くなり、坐骨神経を圧迫することが痛みの原因につながるとされています。痛みが脚の後ろ全体に広がる場合や、しびれを伴う場合には、神経性の要因を考慮することが大切だと言われています。
(引用元:足裏屋クリニック https://ashiuraya.com/information/太ももの裏の筋が痛い|原因を探ってセルフケア/、医療法人全医会 https://www.zenii.or.jp/column/)
その他の要因(姿勢・骨盤のゆがみ・筋膜の緊張など)
一方で、明らかなケガや神経の異常がなくても、姿勢の崩れや骨盤のゆがみ、筋膜の緊張などが太ももの裏の痛みを引き起こすことがあるとされています。特に、長時間のデスクワークや猫背姿勢では、ハムストリングスが常に引っ張られた状態になり、血流が滞りやすくなる傾向があります。また、運動不足でお尻の筋肉(大殿筋)が使われにくいと、太ももの裏ばかりに負担が集中してしまうことも少なくありません。普段の姿勢や体の使い方を見直すことが、改善の第一歩につながると考えられています。
(引用元:Rehasaku https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/、くまのみ整骨院https://kumanomi-seikotu.com/blog/)
#太ももの裏の痛み
#ハムストリングス損傷
#坐骨神経痛
#梨状筋症候群
#骨盤のゆがみ
3.今すぐできるセルフケアと注意点

痛みが出た直後の「応急ケア」(安静・冷却・動かしすぎない)
太ももの裏の筋が痛いと感じた直後は、まず「安静・冷却・圧迫・挙上(RICE処置)」が基本と言われています。痛みを我慢して動かすと、筋線維の損傷が広がる可能性があるため、無理は禁物です。最初の48時間程度は、氷や保冷剤をタオルで包み、15〜20分を目安に冷却します。その後は痛みの程度を見ながら、必要以上に動かさず、安静を保つことが大切とされています。また、湿布を貼る際は皮膚刺激に注意し、長時間の使用を避けるようにすると安心です。強い痛みが続く場合や腫れが出る場合には、整形外科などで検査を受けることがすすめられています。
(引用元:リハサク https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/、くまのみ整骨院https://kumanomi-seikotu.com/blog/7329/)
軽〜中程度の痛みに対するストレッチ・筋膜リリース・姿勢改善の方法
痛みが落ち着いてきたら、筋肉の緊張をやわらげるストレッチや筋膜リリースを取り入れると良いと言われています。椅子に座り、片脚を前に伸ばして上体を軽く前に倒すだけでも、ハムストリングスをゆるめる効果が期待できるそうです。また、テニスボールやフォームローラーを使って太ももの裏をやさしく転がす筋膜リリースも有効とされています。力を入れすぎず、痛気持ちいい程度を目安に行うのがポイントです。
さらに、姿勢のクセも見直してみましょう。猫背や骨盤の後傾は太ももの裏に負担をかけやすいと言われています。デスクワーク中は、腰を少し立てて座ることを意識し、1時間に1回は立ち上がって軽くストレッチするだけでも血流が改善しやすくなります。
(引用元:メディカルID https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/、にっこり鍼灸整骨院https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6042.html)
やってはいけないこと・無理をしてはいけない動き
太ももの裏の筋が痛いときに「早く改善したい」と焦って強いストレッチやマッサージを行うのは避けた方が良いとされています。特に痛みを感じながらの前屈運動や、ランニング・ジャンプ動作などは再損傷の原因になることがあるそうです。また、痛みを隠してトレーニングを続けると、筋膜炎や神経の炎症が長引くケースもあるとされています。
「少し動かしたら良くなるかも」と思うよりも、「いったん休ませて様子を見る」ことが結果的に早い改善につながる場合が多いと言われています。無理のない範囲で、徐々に動きを戻すのが理想です。
(引用元:リハサク https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/、足裏屋クリニックhttps://ashiuraya.com/information/太ももの裏の筋が痛い|原因を探ってセルフケア/)
#太ももの裏の痛み
#セルフケア
#ハムストリングスストレッチ
#筋膜リリース
#姿勢改善
4.受診・検査・治療が必要なサイン

こんなときは整形外科・整骨院へ(しびれ・長期間・腫れ・動かせない)
太ももの裏の筋が痛いとき、「ただの筋肉痛かな」と思って放置してしまう方も少なくありません。ですが、次のような症状がある場合は、整形外科や整骨院での来院がすすめられています。
- 痛みが2週間以上続く
- しびれや感覚の鈍さを感じる
- 腫れや熱感が強い
- 膝や股関節の動きが制限されている
- 座る・立ち上がるだけで痛みが走る
これらの症状は、筋肉の損傷だけでなく、神経や関節、腱などの炎症が関係していることがあるとされています。特にしびれを伴う場合は、坐骨神経への圧迫など、早めの検査が必要になるケースもあります。自己判断でストレッチやマッサージを続けると、かえって悪化することもあるため、専門家に状態を確認してもらうことが重要です。
(引用元:リハサク https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/、にっこり鍼灸整骨院https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6042.html)
医療機関での検査や診断(MRI・神経伝導・触診など)
整形外科ではまず問診と触診を行い、痛みの出る動きや範囲を確認すると言われています。そのうえで、必要に応じてMRIや**超音波検査(エコー)**を用いて、筋肉や腱、神経の損傷状態を確認する場合があります。しびれを伴う場合は、神経伝導検査で神経の働きを調べることもあるそうです。
また、整骨院や鍼灸院では姿勢や骨盤のバランス、筋肉の使い方をチェックし、痛みの原因を見つけて施術方針を決めるケースが多いとされています。検査によって「どこに」「どのような負担がかかっているのか」を把握することが、改善への第一歩につながると言われています。
(引用元:メディカルID https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/、くまのみ整骨院https://kumanomi-seikotu.com/blog/7329/)
治療の選択肢(保存療法・リハビリ・手術など)
太ももの裏の痛みの多くは、**保存療法(安静・湿布・リハビリ)**で改善が見込まれると言われています。まずは痛みを抑えつつ、ストレッチや筋力回復を目的としたリハビリを行うのが一般的です。
一方、肉離れが重度な場合や、神経の圧迫が強いケースでは、医師による注射・薬物療法、またはまれに手術が検討されることもあります。整骨院や理学療法士のサポートを受けながら、痛みの再発を防ぐための筋トレ・姿勢改善を並行して行うことがすすめられています。
重要なのは「焦らず、段階的に改善を目指す」ことです。自己流で負担をかけるよりも、専門家のもとで安全に回復を進めたほうが結果的に早く日常に戻れると言われています。
(引用元:リハサク https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/、足裏屋クリニックhttps://ashiuraya.com/information/太ももの裏の筋が痛い|原因を探ってセルフケア/)
#太ももの裏の痛み
#整形外科受診
#MRI検査
#保存療法
#リハビリ
5.再発を防ぐための予防と日常習慣

ハムストリングス・骨盤まわりの筋力・柔軟性を高めるトレーニング
太ももの裏の筋が痛い原因の多くは、ハムストリングスの柔軟性不足や骨盤まわりの筋力バランスの乱れだと言われています。再発を防ぐには、筋肉を「柔らかく・強く」保つことが大切です。
おすすめのトレーニングとしては、ハムストリングスストレッチとヒップリフトがよく紹介されています。ストレッチでは、片脚を前に伸ばして上体を軽く倒し、太ももの裏をじんわり伸ばすように意識します。呼吸を止めず、反動をつけないのがコツです。ヒップリフトでは、仰向けで膝を立て、お尻をゆっくり持ち上げて骨盤を安定させる動きを繰り返します。これにより、太ももの裏とお尻の筋肉が連動して働くようになり、再発防止につながるとされています。
(引用元:リハサク https://rehasaku.net/magazine/lowerleg/backofthigh-pain/、メディカルIDhttps://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/)
デスクワーク・立ち仕事における「負担をためない姿勢・動き」ポイント
長時間の同じ姿勢は、太ももの裏への負担をじわじわとため込む原因になると言われています。デスクワークでは、椅子に深く座り、背筋を軽く伸ばしながら骨盤を立てるよう意識しましょう。背もたれにクッションを使うと、骨盤が後ろに傾くのを防ぎやすくなります。
立ち仕事の場合は、左右の脚に均等に体重を乗せ、同じ姿勢を長く続けないことがポイントです。数分ごとに軽く体を揺らす、足踏みをするなど、血流を促す動きを取り入れると良いとされています。
また、冷えも筋肉を硬くする要因の一つです。太ももやお尻を冷やさないように意識するだけでも、筋の緊張を防ぎやすいとされています。
(引用元:くまのみ整骨院 https://kumanomi-seikotu.com/blog/7329/、足裏屋クリニックhttps://ashiuraya.com/information/太ももの裏の筋が痛い|原因を探ってセルフケア/)
痛みを繰り返さないために知っておきたい“習慣”&“チェックリスト”
痛みを再発させないためには、「普段のクセ」を見直すことが大切だと言われています。以下のチェックリストで、自分の生活を振り返ってみましょう。
- 朝起きた直後にストレッチをしていない
- 座る時間が1時間以上続くことが多い
- 片脚重心になりやすい
- 運動後のクールダウンを省きがち
- 睡眠時の姿勢が悪く、腰が沈むベッドを使っている
これらに思い当たる項目が多い人は、太ももの裏だけでなく、腰や骨盤まわりにも負担がかかっている可能性があるとされています。生活習慣を少しずつ改善することで、痛みを繰り返しにくい体づくりにつながると言われています。
(引用元:にっこり鍼灸整骨院 https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6042.html、メディカルIDhttps://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/)
#太ももの裏の痛み
#再発予防
#姿勢改善
#ハムストリングストレッチ
#日常習慣